
利根川河口堰閘門
ナンバリングと言ったらこれこれ、利根川河口堰を忘れてはいけない。利根川河口堰はすべてのピア(堰柱=ゲートを支える柱ですね)に、このような巨大な切り抜き文字が貼り付けられていてそれはもう壮観なのである。大きさ、色、材質など、どれをとってもナンバリングマニアへ対する過剰なサービスかと思われるほどで、ほとんど団地の棟番号パーツなみのアメニティな仕様である。
当然、1から始まるが、最後の数字は13にもなる。では12枚もゲートが並んでいるのか、と思われるかもしれないが正しくは11枚である。さてここで問題です。柱が13本あるのに、なぜゲート数は12ではなく、11枚なのか。
簡単だ。可動堰用が9枚と、閘門用が2枚だから。
Pを堰柱、Gをゲートとすると、
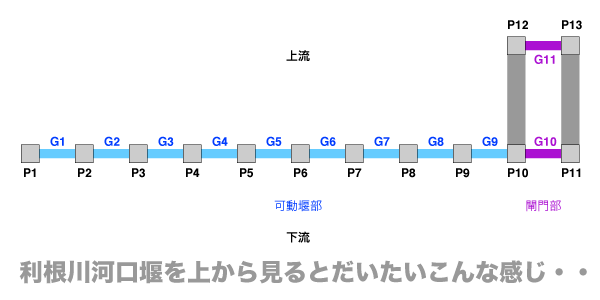
になっているのだ。P10,P11,P12,P13の4本で閘門が形成されている。この写真はG8かG9あたりから撮られていて、可動堰の列から上流側に飛び出したP12とP13を見たものだ。
この程度でオチにするわけにはいかない。本当の問題は、どうしてこんなに立派な仕様のナンバリングがされているか、だ。
もっとも考えられるのは、何か事故があったときに、瞬時に位置を特定するための配慮である。
しかしこれは当たり前すぎて何も推察したことにならない。しかも切り抜き文字である説明がつかない。現に反対側のナンバリングは堰柱へ直接、ペイントでなされているのだ(後付けっぽい)。
光線状態によっては、このように浮き出させた文字の方が視認性が高い、ということもあり得る。このナンバリングのある面は南東を向いており、昼間はおおむね文字の横方向から光が当たるため、この写真のようにいい感じで浮き上がって見える。しかしそれが主目的でもないだろう。機能面からは、切り抜き文字である積極的な意味は発見できないのだ。
となると、単なるシャレ、というかグラフィックデザイン上の処理なのかもしれない。そういやこのナンバリングの書体、普通はこういう場面では使われないフーツラを使っているではないか。そのあたりに、何か設計上の余裕のようなものが見え隠れしてないか。
利根川河口堰は水資源開発公団(現:水資源機構)が、「利根川水系水資源開発基本計画」に基づいて作ったものだ。「利根川水系水資源開発基本計画」と言ったらこれはもうダムを作るための計画のようなものでしょ。つまり利根川河口堰には「ダム並なみの大予算」が投入されており、そのためにこういう設計上のシャレ心を許すようなことができたのではないだろうか。
そういう見方をしていくと、利根川河口堰と隣の黒部川水門は、造形的にもかなり面白い処理のものがあることに思い至る。巻上機器室をゲート上でつなげる時にツライチにしないで、わざと段差を設けていたりとか。同じくモダニズムの文法を使いながらも、他の建設省系の水門にはない個性的なスタイリングになっているのではないか。
こういう土木構造物のデザインの研究って、ちゃんとされているんだろうか。

コメント
反応せずにいられませんでした、フーツラ!
これはフォントマニアにも嬉しい水門です、川の真ん中の5とかも見たいです。
フォントサイズが2m×1.5m、あぁいいですね。
でしょ!
利根川河口堰、もし解体するときはぜひ部品即売会やってほしい!
この切り抜き文字はテーブルなんかに使うといいですね。
> 川の真ん中の5とかも見たいです。
考えておきます。
フーツラは「4」も大いに特徴あり、です。
実はフーツラそのものではなくて、フーツラもどき、なんだけどね。