
こういうのを「陸閘」と言うのだ。水門のゲートだけを陸に上げたもので、まあリクガメ(よくガラパゴスなんかにいるやつ)みたいな存在だ。陸閘の生息地は、東京なら月島晴海地区である。こんな黄緑色のやつがうようよと群生しているのでおどろいてほしい。

いつもはこんな感じでひっそりと隠れているのだ。
陸閘はスライド式のと片開き式のがあって、高潮や津波が予測されるときは電動や手動で閉まる。平時には人や車を通すためにとぎれとぎれになっている防潮堤が、陸閘の出現で連続するのだ。わかりやすいがよく考えるとかなり凄い仕掛け。
陸閘が閉まっちゃうと、その時に防潮堤の外に出ていた人や車は残念ながら戻れない。そんな冷たいことでいいのか、と思う人もいるだろうからちゃんと書いておくと、陸閘にはもちろんハシゴが付いており、それで乗り越えて戻ることはできる。何と車用の脱出ルートも1か所だけ、用意されている。この脱出ルートは平時に見ると、道路のど真ん中に作られたジャンプ台にしか見えない。とにかく東京都港湾局はちゃんと逃げ遅れた人のことを考えているので、安心してください。
さて、問題はこれを水門と見なしていいのかどうか、だ。
理論的にはこれはまぎれもなく水門の一種であると言える。なぜなら狭義の水門は、堤防の分断部分に取り付けられた門扉のことを指すからだ。陸閘も実はこれと全く同じフォーメーションをしている。
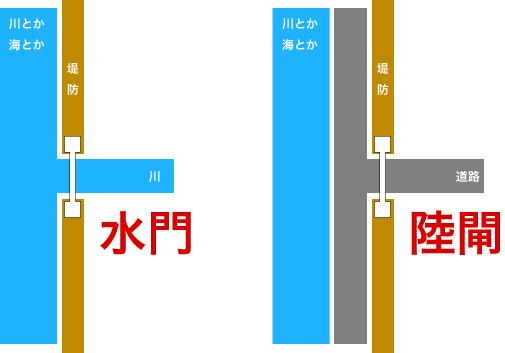
この図を描くまで自分でもいまひとつ自信が持てなかったのだが、これ見たら一目瞭然、陸閘って水門そのものじゃないか。なーんだ。
