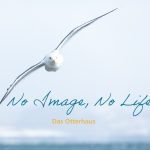群馬県の吾妻川沿いにある、小さな発電所。とってもいとおしい。
こういう発電所を訪れるたびに思うのだけど、水力発電ってこんな小さな発電所がちまちまと発電しちゃってて、大丈夫なんだろうか。何わけのわかんないこと言ってんだと思われそうだけど、こんなかわいい発電所と、原子力発電所や火力発電所の大出力の発電所によって作られる電気と、混ぜちゃっていいのか、という不安なんだけど、余計にわからないですか。酔っぱらってますすいません。
たとえば水道であれば、広域水道で都内でも利根川から荒川を経由してやってくる水を上水道にしている一方で、昔からある地下水を汲み上げて上水道にしている地域もわずかではあるがあるわけで、それが混じることはないと思うのだ。
でも、電気って特定の発電所が特定の地域のための電気を作っている、というような構造になってなくて、東京電力であれば東京電力がもう全体でひとつの回路を成していて、こんな山奥の発電所だろうが東京湾岸の大火力発電所だろうが、要するにつながってるわけだ。
そうすると大出力発電所に対するこんな小さな発電所ってのは、ほとんど誤差のようなものなのではないか。それでもこうやって日々、律義に水車を回して電気を起こし続けている。そんな姿は大変にいおとおしくて、もうたまらない。それってどういう萌えだよ。